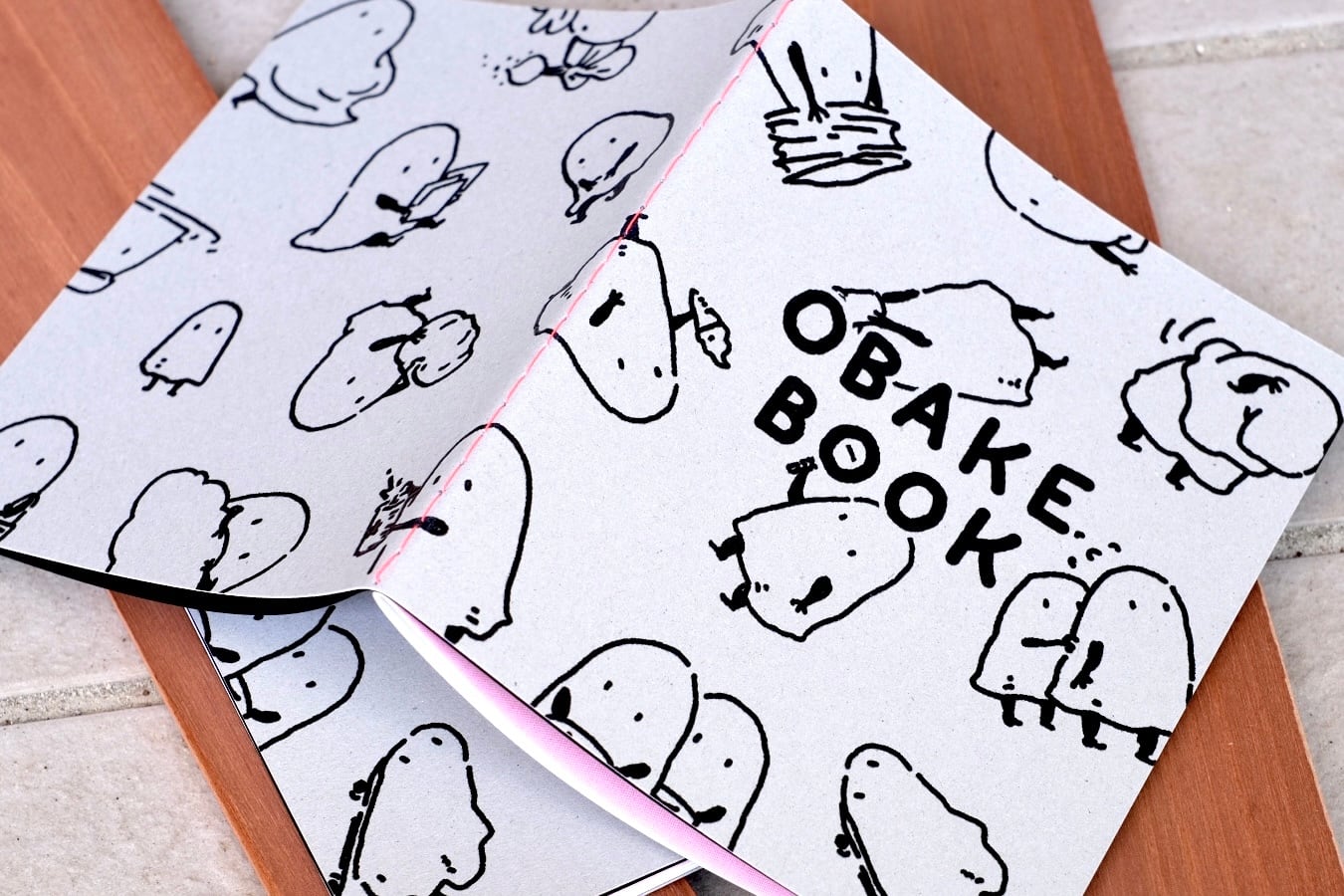Nishikawa Keisuke
・・・
にしかわ けいすけ / NISHIKAWA Keisuke
個人作家としてリソグラフを中心に制作
デザインフェスタ等のイベントに定期出展中
活動の発信はInstagramにて
【リソグラフ作品のご注意事項】
印刷面を擦るとカスれ、
色移りする場合があります。
直接お手をふれないようにお取り扱いください。
印刷の特性により個体ごとに微量な版ズレ、
カスれ、にじみがあり、 WEB上の画像とは
見た目が若干異なる場合があります。
作品の個性としておたのしみください。
過度な日差しにより退色、紙ヤケがおこります。
直射日光を避けて
飾っていただくことをおすすめします。
【返品について】
紙折れ、破れ、水濡れ等の初期不良がありましたら
お取り替えいたします。
CONTACTページから問い合わせください。